「OniGO(オニゴー)×イトーヨーカドーは高い」という声をSNSや口コミで見かけたことはありませんか?
実際に「実店舗より2〜3割高い」といった具体的な投稿や、「ネットスーパーより明らかに高い」という感想もあります。
この記事では、OniGOとイトーヨーカドーの価格差や利用者のリアルな口コミをもとに、本当に高いのか、そしてそれでも選ばれる理由について詳しく解説します。
結論からいえば、OniGO×イトーヨーカドーは割高だが、最短10分で届く利便性を考えれば“必要なときだけ使う”のが賢い選択です。
OniGO(オニゴー)×イトーヨーカドーとは?

OniGO(オニゴー)×イトーヨーカドーは、大手スーパー「イトーヨーカドー」とクイックコマースサービス「OniGO」が連携し、最短10〜30分で商品を届ける宅配サービスです。生鮮食品から日用品まで幅広く揃い、ネットスーパーよりもスピーディーに買い物が完結します。
サービス概要|最短10〜30分で届くクイックコマース
OniGO(オニゴー)は、スマホアプリやWebから注文すると最短10〜30分で商品が届く「クイックコマース」型の宅配サービスです。
生鮮食品や日用品、飲料、惣菜などを幅広く取り扱い、急な買い足しや外出が難しいときに便利。
近隣の「ダークストア(一般客が入らない専用倉庫)」や提携スーパーから商品をピッキングし、配達スタッフが即座に届ける仕組みです。
- 注文方法:アプリまたはWebサイト
- 配送エリア:首都圏を中心に順次拡大中
- 配送料金:一定額以上で無料になるキャンペーンあり
- 決済方法:クレジットカード、各種キャッシュレス決済
イトーヨーカドー提携開始の背景
OniGOはもともと、自社倉庫を拠点にした即配サービスを展開していましたが、品揃えやブランド力を強化するために大手スーパーとの提携を拡大しています。
その中でもイトーヨーカドーとの連携は注目度が高く、2024年後半から一部地域で本格スタート。
提携の背景には以下のような狙いがあります。
- イトーヨーカドー側の狙い
- ネットスーパーよりさらに早く商品を届ける即配モデルを取り入れ、競合との差別化
- 店舗の商圏外や来店困難な層へのアプローチ強化
- OniGO側の狙い
- 大手スーパーのブランド力と信頼感を活用し、新規ユーザーを獲得
- 自社倉庫では扱いにくい生鮮品や惣菜の品揃えを強化
この提携により、利用者はイトーヨーカドーの食品・日用品を最短10分で自宅に届けてもらえるという、これまでのネットスーパーにはないスピード感と利便性を享受できるようになりました。
「高い」と言われる理由
OniGO(オニゴー)×イトーヨーカドーは便利さが魅力ですが、一部の利用者からは「価格が高い」との声も上がっています。実店舗やネットスーパーとの比較で明らかになった価格差や、即配サービス特有のコスト構造について解説します。
- 実店舗との価格差(例:米5kgが4,700円など具体例)
- ネットスーパーとの価格比較
- 即配サービスゆえのコスト構造(人件費・物流費・鮮度維持コスト)
実店舗との価格差がある
利用者の口コミで多く見られるのが、イトーヨーカドー実店舗より2〜3割高いという指摘です。
例えば、SNSでは「米5kgが4,700円と高額だった」という具体的な投稿もあり、他の商品でも玉子や総菜などが数十円〜百円単位で上乗せされているケースが報告されています。
この差額は、同じブランド・同じ内容量でも、OniGO経由のほうが割高になる傾向があることを示しています。
ネットスーパーとの価格比較でも高め
イトーヨーカドー公式のネットスーパーと比べても、「OniGOは明らかに高い」という意見があります。
ブログレビューや比較記事では、同じ日・同じ商品で注文した場合に、OniGOのほうが全体的に価格が高くなるという結果が出ています。
特に、生鮮食品や総菜など単価が安く見える商品でも、積み重ねると1回の注文で数百円〜1,000円以上の差になることも少なくありません。
即配サービスならではのコスト構造
OniGOは「最短10〜30分で配達」というスピードが強みですが、この即配体制を維持するためには人件費・物流費・鮮度管理コストが通常より多くかかります。
- 人件費:注文ごとにスタッフが素早くピッキング・配送
- 物流費:小口配送を頻繁に行うため、配送効率が低い
- 鮮度維持コスト:温度管理や即日配送の体制を常時確保
これらのコストは商品価格に反映されるため、「スピードと引き換えに価格が上がる」構造になっているのです。
OniGO(オニゴー)×イトーヨーカドーの実際の口コミ・評判まとめ
利用者の口コミを総合すると、OniGO×イトーヨーカドーは「価格が高いが便利」という評価が多く見られます。実店舗やネットスーパーより割高という声が目立つ一方、最短10〜30分で届くスピードや品揃えを理由にリピートする人も少なくありません。
- Twitter/SNSの声(実店舗より2〜3割高い)
- ブログレビューの感想(買い物中に胸のザワつきが止まらないなど)
- 配達遅延や不足品対応に関する不満
Twitter/SNSの声|実店舗より2〜3割高い
SNS上では、「イトーヨーカドーの店舗より2〜3割高い」という投稿が目立ちます。
実際の声では、米5kgが4,700円と高額だったケースや、日用品や生鮮食品のほとんどが店舗価格より高く設定されていたといった指摘もありました。
短時間配送の便利さは評価されつつも、「日常使いには割高感がある」という意見が多く見られます。
ブログレビューの感想|“胸のザワつきが止まらない”価格差
あるブログレビューでは、イトーヨーカドーのネットスーパーや店舗とOniGOを比較した結果、同じ商品でも数十円〜百円単位で上乗せされていたとのこと。
著者は「買い物中に胸のザワつきが止まらなかった」と表現しており、価格の高さが心理的な負担になった様子がうかがえます。
一方で、注文から30分以内に届くスピード感や品揃えには満足している声もあり、価格とのトレードオフが議論の的になっています。
配達遅延や不足品対応に関する不満
口コミの中には、価格だけでなく配送体験に関する不満も報告されています。
「予定時間より2時間遅れて到着した」「不足品の代替が雑だった」といった声があり、特に繁忙期やセール時にトラブルが発生しやすい傾向があるようです。
価格が高い上にこうした不満が重なると、リピート利用を控えるきっかけになる可能性もあります。
OniGO(オニゴー)×イトーヨーカドーが「高くても使う」人の理由
割高と感じながらもOniGO×イトーヨーカドーを選ぶ人は少なくありません。その理由は、圧倒的な配送スピードや安定した品揃え、クーポンや送料無料などの特典にあります。
- とにかく早い(最短10分配送)
- 欠品が少ない/品揃えが安定
- 初回クーポン・送料無料キャンペーンの存在
とにかく早い|最短10分配送のスピード感
OniGOの最大の強みは、注文から最短10〜30分で商品が届くスピードです。
急な来客や買い忘れ、体調不良で外出できないときなど、「今すぐ欲しい」というニーズに応えられるため、多少割高でも利用価値を感じる人が多くいます。
ネットスーパーの通常配送(数時間〜翌日)と比べると、この差は圧倒的です。
欠品が少なく、品揃えが安定
イトーヨーカドーとの提携により、生鮮食品・総菜・日用品まで安定した在庫が確保されています。
他の即配サービスでは欠品や代替商品が多くなることがありますが、OniGO×イトーヨーカドーではそのリスクが比較的少ないという声も。
「欲しい商品が確実に届く安心感」が、価格以上の価値につながっています。
初回クーポン・送料無料キャンペーンの存在
新規ユーザー向けには初回割引クーポンや送料無料キャンペーンが用意されており、初回利用時は割高感を感じにくいのもポイント。
さらに、キャンペーンをうまく活用すれば、実店舗やネットスーパー並み、あるいはそれ以下の価格で利用できることもあります。
常時ではなく「セールやクーポンが使えるときだけ利用」というスタイルを取る人も少なくありません。
OniGOを賢く使う方法
OniGO×イトーヨーカドーは便利ですが、日常使いすると割高になりがちです。セールやクーポンを活用し、利用シーンを絞ることでコストを抑えながら快適に使えます。
- セール・クーポン併用で割高感を減らす
- 緊急時や重い商品の購入に限定する
- 他のネットスーパーとの使い分け
セール・クーポン併用で割高感を減らす
初回30%OFFや送料無料キャンペーンなどを利用すれば、実店舗やネットスーパー並みの価格になる場合があります。定期的なプロモーションもあるため、注文前にアプリやWebで最新クーポンを確認しましょう。
緊急時や重い商品の購入に限定する
急ぎで必要な食品や、米・飲料・調味料などの重い商品は、持ち帰りの手間を考えると多少割高でも即配の価値があります。必要なときだけスポット利用すれば、出費を最小限にできます。
他のネットスーパーとの使い分け
普段のまとめ買いはイトーヨーカドー公式ネットスーパーや他サービスを使い、急ぎのときはOniGOを使う「ハイブリッド利用」がおすすめ。利便性とコストのバランスを取りやすくなります。
まとめ|価格と利便性のバランスを見極めよう
OniGO×イトーヨーカドーは、確かに実店舗やネットスーパーより割高になるケースが多いものの、その分「最短10分配送」という他にない利便性を提供しています。
「高い」という指摘は事実ですが、重い荷物を持ち帰る負担や、急な買い物の時間ロスを考えると、時短と即配の価値は大きいと言えます。
普段使いよりも、必要なときだけ賢く利用するスタイルを選べば、コストと便利さの両立が可能です。

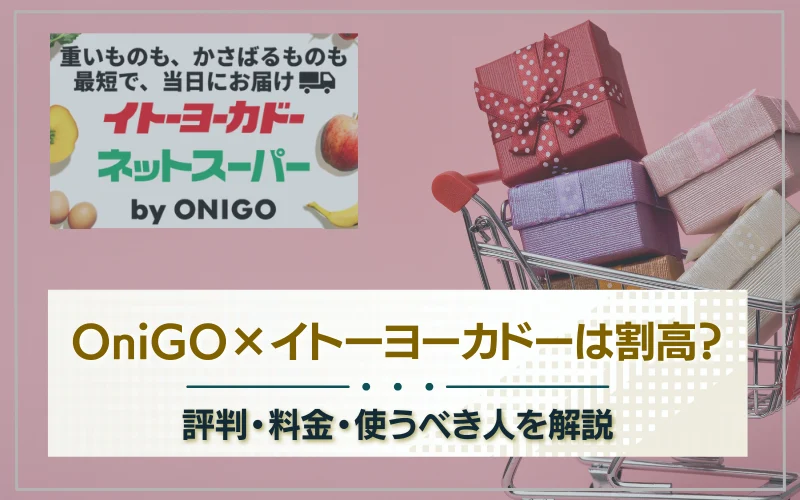

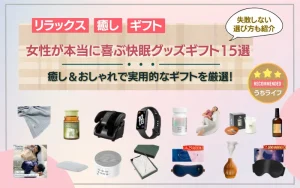

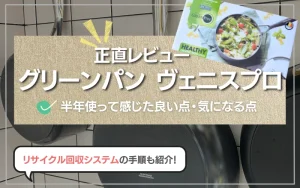

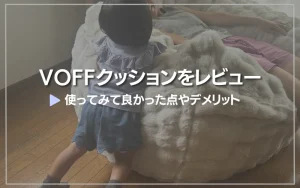


コメント