「最近、肌のハリがなくなってきた」「年齢とともに疲れが抜けにくい」
──そんなエイジングサインを感じている方に注目されているのが、次世代成分「5-デアザフラビン」です。
近年では、NAD再生やサーチュイン遺伝子との関係から、“若返り効果が期待される素材”として話題になりつつあります。
この記事では、5-デアザフラビンがなぜエイジングケアに役立つとされているのか、研究知見や仕組み、他の若返り素材との違いなどをわかりやすく解説します。
見た目も内側も“若々しさ”をキープしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
5-デアザフラビンが“若返り素材”と呼ばれる理由
5-デアザフラビンが“若返り素材”として注目されている背景には、体内の老化メカニズムと深く関わる3つの働きがあります。
- NADの再生 → エネルギー代謝活性化
- SIRT1などの長寿遺伝子が活性化する仕組み
- 細胞老化の抑制=“細胞年齢”を若く保つ
NADの再生を促進し、エネルギー代謝を活性化
加齢とともに体内で減少する「NAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)」は、細胞のエネルギー生産や修復機能に不可欠な物質です。
5-デアザフラビンは、このNADを再生・維持する補酵素の働きを助けるとされ、代謝機能の低下を防ぐ点で注目されています。
エネルギー代謝の活性化は、疲れにくい体づくりや肌のハリ・つやの維持にも関係すると考えられています。
長寿遺伝子「サーチュイン(SIRT1)」の活性に関与
“長寿遺伝子”として知られるSIRT1(サーチュイン1)は、細胞の修復や炎症抑制、老化の抑制に関わる遺伝子です。
SIRT1の働きはNADによって活性化されるため、NADをサポートする5-デアザフラビンの間接的な作用が期待されています。
研究段階ではありますが、加齢による細胞機能の低下に対抗する鍵として、SIRT1の活性化はエイジングケアの重要なテーマとなっています。
細胞老化を防ぎ、“細胞年齢”を若く保つ
老化とは見た目だけでなく、細胞の中でも起きている現象です。DNAの損傷・ミトコンドリア機能の低下・酸化ストレスなどが進むと、細胞は“老化細胞”へと変化し、代謝や再生能力が落ちていきます。
5-デアザフラビンは、細胞内でのエネルギー循環や修復活動を助けることで、こうした老化現象の進行を緩やかにすると期待されています。
“見た目の若さ”の前に、“細胞レベルの若さ”を維持すること──それがこの素材の大きな可能性です。
エイジングケア研究で注目される成分との比較
近年、さまざまな“若返り成分”が研究・開発されていますが、その中でも特に注目されているのが、NMN・NR・5-ALA・そして5-デアザフラビンです。
いずれも細胞レベルのエイジングケアに関わるとされる成分ですが、それぞれに特徴や研究の進み具合が異なります。
| 成分名 | NAD再生 | ミトコンドリア活性 | 研究段階 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|
| NMN | ◎ (前駆体) | 〇 | 進行中 (ヒト研究あり) | アンチエイジング |
| NR | ◎ (前駆体) | 〇 | 進行中 | 代謝・活力 |
| 5-ALA | △ (直接関与なし) | ◎ | 進行中〜応用 | 疲労・糖代謝・免疫 |
| 5-デアザフラビン | 〇 (補酵素的作用) | ◎ (維持作用) | 初期 (動物実験・細胞研究) | NADサポート 細胞老化抑制 |
NMN(ニコチンアミドモノヌクレオチド)
NAD+の前駆体として最も有名な成分。ハーバード大学などでの研究により、マウスでの寿命延長・筋力維持・代謝改善が示され、「抗老化素材の筆頭格」として注目されています。
ただし、ヒトでの有効性はまだ予備的段階であり、1日300mg以上など高用量が必要という指摘もあります。
NR(ニコチンアミドリボシド)
NMNと同様にNAD+の前駆体。吸収性が高いとされ、サプリメント素材として多く流通しています。
研究データの蓄積も進んでいますが、NMNとの違いはややマイナーで、代謝経路における有効性の比較は議論中です。
5-ALA(5-アミノレブリン酸)
ミトコンドリアのエネルギー産生を助ける素材で、主に代謝改善や疲労回復を目的とした研究が多いです。
糖尿病・睡眠改善・免疫サポートなど幅広く活用されており、医薬品成分としての利用も進行中。
ただし、NAD回復には直接的に関与しないため、“若返り”というよりは「健康維持」のイメージに近いかもしれません。
5-デアザフラビン
補酵素としてNAD再生に関与する“触媒系の新素材”。他の素材が“材料”なのに対し、5-デアザフラビンは“燃焼を助ける火花”のような役割を果たします。
まだ研究段階ではありますが、NADの回復効率・ミトコンドリア活性の持続性において有利な可能性が指摘されています。
NMNなどと組み合わせることで、より効率的なNAD再生を目指す用途としても期待されています。
40代以降が注目すべき理由|“代謝の曲がり角”と5-デアザフラビン
40代に差しかかると、「疲れが抜けにくい」「肌のハリがなくなってきた」「朝起きるのがつらい」といった“なんとなく不調”を感じやすくなります。
この背景には、体内のNAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)レベルの急激な低下があると考えられています。
5-デアザフラビンは、40代以降に急激に低下するNADレベルを効率的に再生し、代謝の衰えによるエイジングサインに内側からアプローチできる可能性がある成分です。
加齢によってNADは大幅に減少する
NADは、エネルギー代謝・細胞修復・サーチュイン遺伝子の活性など、いわば若さを保つエンジンの燃料のような存在です。
しかし、NADは加齢とともに減少し、50代では20代の半分以下にまで低下するともいわれています(※マウス研究ベース)。
これが「代謝の曲がり角」と呼ばれる40代前後からの不調の一因だと考えられています。
5-デアザフラビンは“燃料の再生”を助ける
NMNやNRのようにNADそのものの材料を補う方法もありますが、5-デアザフラビンはそれを“再生・循環させる”補酵素的な働きを持つ点が特徴です。
エネルギー代謝が落ちてくる40代以降において、限られたNADを効率的に回すという視点は、加齢対策として非常に合理的といえるでしょう。
“なんとなく老けて見える”のは代謝のせい?
肌のターンオーバー、髪の艶、筋肉量、内臓脂肪、疲労回復力――これらの変化はすべて代謝と深く関わっています。
NADを中心としたエネルギー代謝の低下は、見た目だけでなく“細胞年齢”の加速にもつながります。
だからこそ、40代以降のエイジングケアでは「スキンケアだけでなく代謝ケアも必要」という考え方が広がっています。
5-デアザフラビンは、そうした内側からの若返りを支える“新しい選択肢”として注目されているのです。
医師・専門家の見解「美容目的での使用はどう見るか」
現在、公表されている研究の多くは動物実験や細胞レベルの報告にとどまり、ヒトを対象とした臨床試験はまだ初期段階です。
以下は、5‑デアザフラビン(TND1128)に関する専門家のコメントです。
ソジョウ大学 永松理教授
「5‑デアザフラビン(TND1128)は、β‑NMNと比較して、マウスの神経樹状突起の発達や細胞活性化においてより顕著な作用が確認されており、活力増強や老化予防において有望な成分となる可能性があります。」
このように、専門家の視点では「NMNより優れるかもしれない」という動物モデルでの知見が報告されています。一方で、医師レベルによる美容目的の使用に対する正式な推奨コメントは現段階ではなく、ヒトへの有効性・安全性は不確かな状態です。
美容目的での利用には「期待される可能性」と「まだ確立されていない」という両面の理解が重要です。
評判や効果、エビデンス資料については「5-デアザフラビンは怪しい?本当の効果とリスクを徹底検証」も確認してみてください。
5-デアザフラビンを活かす3つの生活習慣
5-デアザフラビンの働きを最大限に引き出すには、ただ摂取するだけでなく、日常の生活習慣と組み合わせることが大切です。以下の3つは、エビデンスにもとづいた実践的なポイントです。
- 空腹時間(ファスティング)と組み合わせる
- ミトコンドリアを活性化する運動習慣
- 抗酸化食材との同時摂取
空腹時間(ファスティング)と組み合わせる
短時間のファスティング(例:16時間断食)は、NADレベルやサーチュイン遺伝子の活性に良い影響を与えることがわかっています。
5-デアザフラビンはNADの再生をサポートするため、ファスティング中の摂取や断食後のタイミングで併用すると、代謝のリセット効果が期待できます。
ミトコンドリアを活性化する運動習慣
ウォーキングや軽い筋トレ、有酸素運動は、ミトコンドリアの数と質を高める有効な手段です。
5-デアザフラビンの“ミトコンドリア活性化作用”をより活かすには、運動による刺激との相乗効果が有効です。
特に40代以降は、習慣的な運動によって“細胞の若さ”を維持しやすくなります。
抗酸化食材との同時摂取
老化の大きな原因のひとつが「酸化ストレス」。ビタミンCやE、ポリフェノール、アスタキサンチンなどの抗酸化成分を含む食材と一緒に摂取することで、細胞へのダメージを抑えやすくなります。
5-デアザフラビンはエネルギー代謝に関与しますが、同時に抗酸化環境を整えることで、より安定してその機能を発揮できると考えられます。
まとめ|“若返り素材”としての未来に期待を寄せつつ、賢く活用を
5-デアザフラビンは、NADの再生やサーチュイン遺伝子の活性といったメカニズムを通じて、エネルギー代謝や細胞の若々しさをサポートする新素材として注目されています。
特に40代以降の“代謝の曲がり角”を迎える世代にとっては、細胞レベルからのアプローチとして取り入れる価値がある成分です。
一方で、ヒトへの明確な効果や長期的な安全性についてはまだ研究途上である点も見逃せません。美容・健康目的での活用には、信頼できる情報や製品をもとに、あくまで「自分の体に合うかどうか」を見極める視点が重要です。
今後の研究によって、さらにその可能性が明らかになることが期待される5-デアザフラビン。
食事・運動・生活習慣と組み合わせて、賢く・無理なく取り入れていくことが、持続的なエイジングケアの鍵となるでしょう。

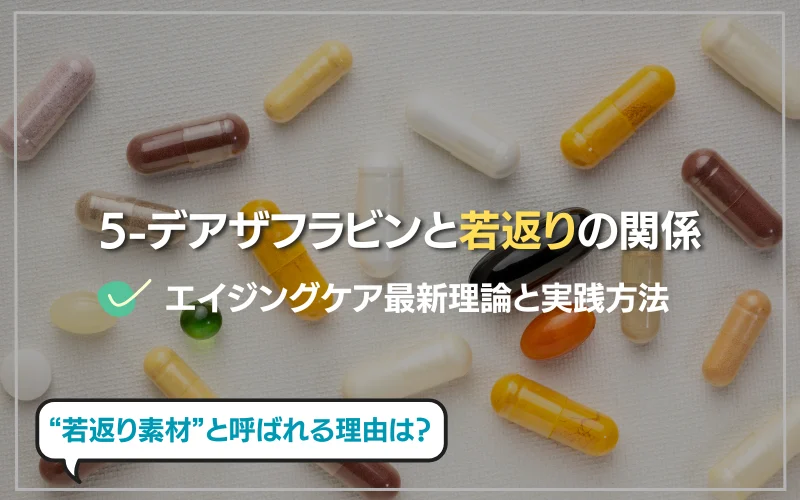



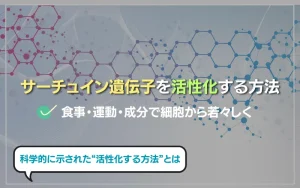


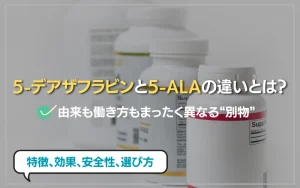
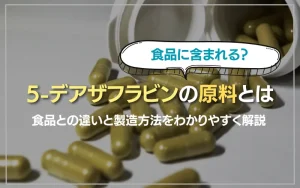
コメント